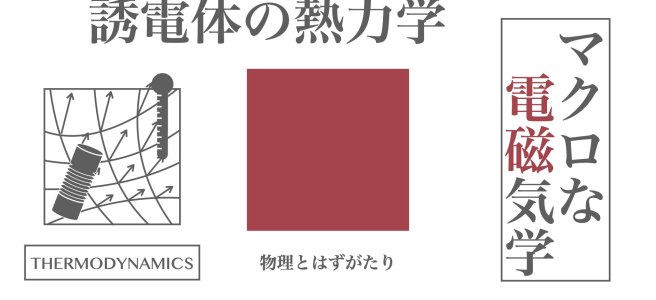この節では誘電体の熱力学を考える.
導体の場合は内部に静電場は作られず物性に影響を与えない.
一方で誘電体では内部の電場は分極場を生じ有効的な静電場は真空中とは異なる値(異方的な場合は異なる向きも)をもつ.
こうした分極による物性は一般には状態方程式 ,あるいは線型な範囲では誘電率テンソル
に込められる.
まず誘電体のエネルギーを計算しよう.
そのために導体のエネルギーの表式を利用する.
空間全体に誘電体が満たされていて,そこに導体 を考える.
誘電体が存在する領域は .
導体の電荷を と(断熱的に)変化させたときのエネルギーの変化は

とかける. は導体表面上の静電ポテンシャルで定数.
この操作によって系の静電場は変化してしたがってエネルギーも変化する.
導体内部では静電場が存在しないからこれは外部電場中の誘電体のエネルギーの変化とみなせる.
Gaussの法則により

が成り立つ.
電荷密度は導体表面上でのみ値を持ち,両辺を導体上で積分すると

が成り立つ.
よってエネルギーの変分は

とかける. は境界上で一定なので積分の中に入れることができ,さらにGaussの定理を再度用いることで誘電体上の積分に書き換えて

法線ベクトルが逆向きになることに注意せよ.
発散を展開すると となる.
誘電体内に自由電子は存在しないので でありGaussの法則より
となって第1項はおちる.
第2項では保存力条件 により

導体内部では静電場が存在しないので積分は全空間に広げても良い.
すなわち導体の存在には関係ない一般的な式である.
これが求めるエネルギーの表式である.
熱力学第一法則からは

を得る.
準静的過程の場合は無限小の変位を定義できて微分形式の関係式

となる. はそれぞれ系の温度,圧力,化学ポテンシャル.
この式では積分の微小体積要素 と微小変位
が紛らわしい.
そこで各熱力学変数の密度を

などと定義する.
内部エネルギーは変数 の函数だが密度にすると1つを取り除くことができて
で表される.
微分形式では
誘電体の熱力学関係式

となる.
1階の偏導函数については

である.
ここで は
成分以外を固定することを意味する.
Legendre変換によりHelmholtzの自由エネルギーの密度は

さらに静電場と電束密度についてのLegendre変換も考えることができて


温度と粒子数が一定の系を考える.
Helmholtzの自由エネルギー最小の原理により,この系において実現される静電場 はHelmholtzの自由エネルギー
を最小にする.
ただし電束密度 は拘束条件としてGaussの法則と境界条件

を満たさなければならない.
1つ目の表式は誘電体内部で成り立つことに注意.
また は導体表面上の電荷.
そこでLagrangeの未定乗数法により

を定義する.
ただし は変分により決まる定数.
註) の拘束条件は通常のLagrangeの未定乗数法だが,
は場の配位についての局所的な拘束条件であり汎函数のLagrange未定乗数法が適用されることに注意せよ.
場の変分 に対して

微分の関係式から .
また右辺第2項で

と変形してGaussの定理を適用すれば

となる.
したがって のためには

が導かれる.
すなわち静電場はあるスカラー函数の勾配でかける.
またそのスカラー函数は導体との境界上で一定値を取る.
これは が静電ポテンシャルであることを示す.
熱平衡状態ではHelmholtzの自由エネルギーが最小なので,そこからの(等温の)仮想的な変異をとると必ず増大する; .
等温の条件下で2次の変分の項は

について平方完成すれば

となる.
自由エネルギー が最小となるためには2次の変分が正でなければならない.
まず ,すなわち

がわかる.
さらに行列 が正定値行列(固有値が全て正)でなければならない.
Jacobianを用いた変形により

後ろの因子は正だから結局,温度と化学ポテンシャルを固定したときの が正定値行列でなければならない.
特に線型な関係 の場合は
.
正定値行列の逆行列もまた正定値なので

が導かれる.
註)ここでは任意の成分が正という意味ではなく正定値であるという意味で不等号を使っている.
Next
- 定常電流